- [2025年7月9日]
- ID:3796
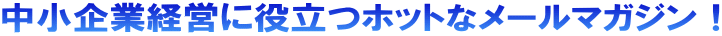

連載
中小企業が売上を伸ばすためのブランディング
日本フルサポート株式会社 代表取締役 荒木 真喜子
第1回 中小企業が売上を伸ばすためのブランディング (2025/4/17発行 第1010号 掲載)
第2回 売上の式から読み解くブランディング (2025/5/8発行 第1012号 掲載)
第3回 「高くても選ばれる」には(2025/5/22発行 第1014号 掲載)
第4回 ブランドは記憶から生まれる (2025/6/5発行 第1016号 掲載)
第5回 ブランド人格とは何か (2025/6/19発行 第1018号 掲載)
第6回 ブランドは自走する (2025/7/3発行 第1020号 掲載)
第1回 うちは関係ない?ブランディングの誤解を解く~小さな会社にこそ必要な、「価値の設計」~
■ブランディングは、儲からない?
「ブランディングをすると儲かるんですか?」
そう聞かれたとき、私はこう答えます。
「はい、儲かります。ただし、“正しく”取り組めば。」
しかも、儲かるだけではありません。ブランディングは、こんな悩みにも効果を発揮します。
-安売りが続いている
-広告を出しても反応がない
-お客様が定着しない
-採用がうまくいかない
一見バラバラに見えるこれらの課題も、実は「根っこ」が同じかもしれません。
そして、これらの課題を解決に導くのが、ブランディングの力です。
ブランディングとは、「価値で選ばれ、自然に売れる仕組み」を整えること。
だからこそ、しっかり利益が残るのです。
この連載では、売れない時代をしなやかに、そして強く生き抜くための実践的なブランディングについて、全6回でお届けします。
「できそう」「やってみよう」と思っていただけたら幸いです。
■私も“誤解”していたブランディング
私は現在、中小企業診断士として活動していますが、以前は約20年間、ホテルを経営していました。
当時の私は、「ブランディング=ロゴや広告、企業イメージをよく見せること」だと誤解していました。
いま振り返れば、もっと早くブランディングに取り組んでいれば、経営はずっと楽になっていたと思います。
■誤解1:小さな会社にブランディングは不要?
皆さんは、「うちは小さな会社だから関係ない」「BtoBだから必要ない」「一人でやっているから意味がない」
そう思っていませんか?それは大きな誤解です。
ブランディングは、業種や規模にかかわらず、すべての事業に欠かせない戦略です。
■誤解2:大企業と同じやり方でいい?
実は、大企業と中小企業では、ブランディングの進め方がまったく異なります。
ところが多くのブランディング関連書籍やセミナーでは、
「名前を思い出してもらえるか(=想起)」を中心に語られ、事例は大企業ばかり。
多額の広告費や専門スタッフが前提となっているケースも少なくありません。
そのため、多くの中小企業は「うちには無理だ」と感じてしまうのです。
中小企業のブランディングに必要なのは、「大きな資金」ではなく、「伝える意志」と「価値の設計」です。
■誤解3:ブランディング=差別化?
たしかに、“違い”は大切です。
でも、今は良いモノがあふれる時代。品質や価格だけの差別化には限界があります。
奇抜さや話題性で一時的に注目されても、持続的な成果にはつながりません。
ブランディングに必要なのは、単なる差別化ではなく、「価値の設計」です。
■「価値の設計」が明暗を分けた和菓子店の事例
では、「価値の設計」について、ある老舗の高級和菓子店を例に考えてみましょう。
この店は、味には自信があり、長年の常連に支えられてきました。
しかし、「語らずとも、伝わるはず」と考え、情報発信にはあまり力を入れてきませんでした。
やがて常連のお客様の高齢化とともに売上が減少。
若い世代からは「特徴がわからない」と言われ、新規顧客の獲得が難しくなりました。
一方、近くに開店した新しい和菓子店は、お客様との日々の会話から要望を拾い、それを商品や店づくりに反映。
さらに、商品に対する想いやこだわりを丁寧に発信し続けたことで共感を呼び、徐々に「選ばれる店」となっていきました。
では、何が違ったのでしょうか?
味?価格?パッケージ?
そのすべてだったかも知れませんし、そのどれでもないかも知れません。
決定的な違いは、「なぜそのお菓子を買うべきか」という理由が、お客様に伝わっていたかどうかです。
つまり、「価値の設計」が売上に明暗をもたらしたのです。
「価値の設計」とは、「誰に、どんな価値を、なぜ私(当社)が届けるのか」を明確にし、それを「伝える意志」を持って、あらゆる接点で一貫して発信できるように整えることです。
商品やサービスはもちろん、接客、SNS、Webサイト、ロゴ、パッケージに至るまで、伝える価値を意図的に揃えていく営みがブランディングです。
その結果、価格ではなく「共感」や「納得」で選ばれるようになり、値引きに頼らず売れるようになる――それが、ブランディングの効果です。
■ブランディングを育てる小さな問い
お客様にとって、「あなた(御社)から買う意義」とは何でしょうか?
ぜひ、考えてみてください。
その問いに向き合うことが、ブランディングの第一歩です。
■次回予告
次回は、「売上=単価×数量」というシンプルな式を使って、マーケティングとブランディングの役割の違いをひも解きます。
第2回 売上の式から読み解くブランディング ~中小企業の「儲け方」は“たくさん売る”ではない~
今回は、「売上=単価×販売数量」というシンプルな式を出発点に、
中小企業が限られた資源の中で、いかにして利益を生み出していくかを考えていきます。
■中小企業が「数を売る」戦略に頼る危うさ
売上は、次の非常にシンプルな式で表されます。
売上=単価 × 販売数量
つまり、売上を上げるためには、単価を高めるか、数量を増やすか、あるいはその両方を行うしかありません。皆さんの会社では、どちらを重視しているでしょうか。
「安くしないと売れない」「価格を上げたいけど、お客様が離れたら困る」
しかし実際には、価格だけで選ばれたお客様は、より安い選択肢が現れた途端に離れていく傾向があります。
価格競争に巻き込まれれば、売上は立っても利益はどんどん削られ、やがて消耗してしまいます。
中小企業は、大手のように、資金力と知名度を武器に、大量生産・大量販売モデルを成立させることはできません。広告費、人員、流通網のすべてにおいて体力差があるからです。だからこそ中小企業は、「価格を下げてたくさん売る」よりも「少ない数でも利益を残す」戦略へと、戦略の軸を切り替える必要があります。
実は私自身、ホテル経営時代にこの罠にはまったことがあります。
周辺の宿泊施設が値下げを始めたとき、「お客様が離れたら困る」と値下げに踏み切ったのです。
しかし、値下げした分だけ収益は減り、客層も「安いから泊まる人」へと変わりました。
当然、お客様との信用も築けず、気づけば体だけでなく精神まで疲弊し、ホテル全体が負のスパイラルへと向かっていきました。価値で勝負せずに、広告や値下げに逃げたことが、最大の過ちだったと強く反省しています。
■ブランディングとマーケティングの役割の違い
では、どうすれば単価を上げ、少ない販売数量でも利益を確保できるのでしょうか?
その答えが、ブランディングにあります。
ブランディングは「選ばれる理由」をつくり、高くても買いたいと思ってもらうことです。
一方、マーケティングは広告や販促など「どう売るか」の手段です。
2つの違いを表にまとめて整理してみましょう。
ブランディングとマーケティングをスポーツに例えるなら、ブランディングは「筋トレ(即効性はないが、積み上げることで長期的な力になる)」、マーケティングは「ドーピング(短期的に結果を出すが、持続しにくい)」。つまり、本来の順序からすれば、まず取り組むべきは筋トレ、ブランディングなのです。
中小企業の儲け方の基本は、単価戦略を軸に「高くても選ばれる」価値を設計し、少ない数量でも利益を残せる持続可能な利益構造を築くことです。数量戦略はその基盤を整えた後にこそ活きる手段であり、順序を間違えないことが成功の鍵です。
■ブランディングを育てる小さな問い
値上げをためらっていませんか?
価格は、自信のなさの表れになっていませんか?
※「ブランディング」や「マーケティング」といった言葉には、明確かつ統一された定義があるわけではありません。そのため書籍などでも解釈はさまざまであり、どちらもより広範な概念を指す場合があります。
本稿では、実務に役立つ視点から、中小企業にとっての「儲け方の構造」の違いに焦点を当て、両者の整理を試みました。
■次回予告
第3回では、「高くても選ばれる」状態をどう設計するか。
その鍵となる「価値の中身」を掘り下げていきます。
第3回「高くても選ばれる」には ~顧客の心を動かす「体験価値」の設計~
今回は、「価格が高くても選ばれる理由」を明らかにするために、価値を要素に分けて考察します。
■「価値の正体」――4つの視点から読み解く
商品やサービスの価値は、単純な一面では測れません。
人は、価値を一つの要素だけで判断するわけではなく、複数の面から総合的に判断しているのです。
価値の中身を分解すると、主に次の4つに分類できます。
・機能的価値:性能、品質、利便性など、数値化しやすく比較しやすい価値
・情緒的価値:安心感、信頼感、癒しなど感情に訴える価値
・自己表現価値:自分らしさやこだわりを表現できる価値
・社会的価値:社会や他者に貢献できる価値
これらが組み合わさることで、顧客の感情が動き、「買いたい」という気持ちが芽生えます。
■高くても選ばれるためには?
高くても選ばれるためには、機能的価値をいくら積み上げても、それだけでは不十分です。
たとえば最新機能を搭載したエアコン。
「機能が多すぎて使わない」「ボタンが多すぎてわかりづらい」――そんな経験はないでしょうか。
重要なのは、単なる機能的価値の向上ではなく、情緒的価値・自己表現価値・社会的価値、つまり「体験価値」をどう設計し、組み込むかです。
■高価格の正体――「価格プレミアム」
たとえば、ある高級馬具メーカーが展開するバッグ。上質な革と丁寧な縫製が特徴ですが、「物を運ぶ」という機能だけで見れば、数千円のバッグとそれほど大きな差はありません。
それでも百万円を超える価格で売れ続けているのは、なぜでしょうか。
・ブランドに対する信頼や、持っていること自体の誇らしさ(情緒的価値)
・自分らしさやステータスを「持ち物」で表現できる満足感(自己表現価値)
・文化や職人を支えているという貢献意識や共感(社会的価値)
つまり、「持つこと自体に意味や価値がある」と人々が感じているからです。
このように、機能を超えて人が“進んで支払う”上乗せ分を、「価格プレミアム」と呼びます。
■「体験価値」は、どんな規模でも設計できる
こうした「価格プレミアム」は、大企業や高級ブランドだけのものではありません。
BtoCはもちろん、BtoBの取引においても、体験価値が「選ばれる理由」になる場面は多く、個人経営や小規模事業者でも十分に生み出すことができます。
たとえば、地域に根ざした町のお弁当屋さん。
コンビニよりも少し高めの価格設定でありながら、常連客が途切れません。
・店主のおばちゃんと話す時間が心地よい(情緒的価値)
・味の好みを覚えていてくれる(自己表現価値)
・地元の食材を使って地域を支えている(社会的価値)
同様に、BtoBの取引においても、以下のような体験価値が考えられます。
・対応の速さ、誠実な提案(情緒的価値)
・当社の価値観や方針を理解した提案(自己表現価値)
・地域企業同士の連携、サステナビリティへの貢献(社会的価値)
このように、BtoC・BtoBを問わず、単なる機能的価値を超えた「体験価値」こそが、価格以上の選ばれる理由になるのです。
■中小企業にとっての「体験価値」設計のヒント
体験価値を構築するには、「どんなお客様が」「どんな気持ちになってほしいのか」を明確にし、それを逆算して設計する視点が必要です。
実は、その設計にもっとも適しているのが、中小企業なのです。なぜなら、中小企業は、大企業のようにマス(大衆)に向けて一律に価値を提供するのではなく、「個客」=目の前の一人、あるいは一社に視点を合わせ、柔軟に応える力を持っているからです。さらに、お客様との距離が近いからこそ、気づいたことを即座に体験価値に反映できるという強みもあります。
この「個客」を起点にした体験価値の積み重ねこそが、中小企業にしか築けない「ブランドの土台」なのです。言い換えれば、体験価値の設計はブランディングの中心であり、中小企業が価格や品質だけに頼らず、独自の価値で勝負するための、頼もしい武器となるのです。
■ブランディングを育てる小さな問い
「高くても選ばれる」体験価値を、皆さんは意図的に設計できていますか?
■次回予告
第4回では、こうして設計した体験価値を、どのように顧客の記憶に刻み、想起へとつなげるか。中小企業にとって重要な「記憶の設計」について掘り下げていきます。
第4回 ブランドは記憶から生まれる ~ロイヤリティを育てる「記憶の仕掛け」~
これまでの回では、「価値の設計」や「高くても選ばれる理由」「体験価値のつくり方」について考えてきました。今回はその一歩先として、記憶に残る体験がどのようにブランドロイヤリティを育てるのか、そしてそれを設計するには何が必要かを掘り下げていきます。
■ブランドロイヤリティとは何か?
ブランドロイヤリティとは、「他にも選択肢があるのに、なぜかこのブランドをまた選びたくなる」。そんな、感情の根底にある愛着や信頼のことを指します。
ただし、ロイヤリティは、製品への満足や一時的な感動だけでは生まれません。
つまり、記憶に残る存在であることが、ロイヤリティの前提として必要なのです。
■なぜ「体験」だけでは不十分なのか?
中小企業の集客は、「偶然の出会い」から始まることが多くあります。
たとえば、SNSの投稿がたまたま目に留まった、歩いているときに見つけた、など。
しかし、そこで選ばれても一度きりの体験で終わってしまえば、次はありません。
だからこそ、その体験を記憶に変える設計が重要になるのです。
■記憶に残すための4つの仕掛け
記憶に残るブランド体験を設計するうえで、次の「4つの心理的な仕掛け」が有効です。
1.初頭効果:「第一印象がすべて」
2.繰り返し効果:「会えば会うほど好きになる」
3.感情の喚起:「心が動けば、記憶が残る」
4.物語化:「語りたくなる話は、忘れられない」
これらの仕掛けはいずれも、心理学や消費者行動の観点から、体験を記憶に昇華させるための鍵です。具体例として、ある鋳物のホーロー鍋ブランドを見てみましょう。
■無名の町工場から、「記憶されるブランド」へ
このブランドは、限られたリソースでスタートしながらも、現在では多くの人の記憶に残り、選ばれる存在へと成長しています。その成長の鍵となったのが、徹底した「記憶の設計」です。
1.第一印象で価値観を伝える――初頭効果
製品スペックよりも先に、ホームページで発信されているのは、「暮らしの質を変える鍋」「手料理と、生きよう。」といった、ブランドの世界観を示すメッセージです。
この“最初のひと言”が、「このブランドは自分の価値観に近い」と感じさせ、強く印象づけます。
2.自然と何度も触れる――繰り返し効果
購入後も、アプリでのレシピ共有やイベント、ニュースレターなど、ブランドに自然と触れる仕掛けが豊富です。こうしたブランドとの接点の積み重ねが、記憶への定着を促します。
3.感謝と貢献の可視化――感情の喚起
ユーザー同士がレシピに「ありがとう」を贈り合える仕組みがあり、コインという形で感謝が可視化されます。「誰かの役に立った」という実感が、貢献感や自己効力感を喚起し、記憶に深く刻まれるのです。
4.語りたくなる背景――物語の力
「0.01mmの密閉性へのこだわり」や「1万個の試作」といった背景は、製品を“語れる存在”に変えます。このストーリーがあることで、「このブランドだから選びたい」という気持ちが自然と育まれるのです。
こうした記憶の積み重ねが、「他ではなく、このブランドを選び続ける理由」になります。
記憶されなければ、ロイヤリティは生まれない――これは、広告に頼れない中小企業にとって非常に重要な視点です。だからこそ、ブランドは意図的に記憶を設計し、関係性を育てる仕掛けをつくる必要があるのです。
■中小企業こそ、「記憶に残る仕掛け」をつくる
では、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
鍵は、共感・参加・対話を促す工夫にあります。
•顧客の「役割」を生み出す仕組み
(例:レシピ開発に参加、製品モニター、イベントへの参加など)
•個人の記憶を「共有体験」へと変える仕掛け
(例:レビューに対する企業からの返信、体験談の紹介、寄せられた声を反映した改善内容の発信など)
中小企業に必要なのは、大きな予算ではなく「記憶に残す知恵」です。
「忘れられない体験」を設計すること――それこそが、選ばれ続けるブランドを育てる第一歩となるのです。
ブランディングを育てる小さな問い
皆さんのブランドは、どんな体験を通じて、どんな記憶を残し、どんな関係を築こうとしていますか?
■次回予告
次回は、こうして記憶に残ったブランド体験を、一貫して伝えるための「ブランド人格」について考えます。
第5回 ブランド人格とは何か 〜内側から“一貫した価値観”を育てる仕組み〜
「記憶に残る体験が、ブランドロイヤリティを育てる」――。
前回はそんな「体験の設計」についてお伝えしました。
ただし、いくら印象的な体験を届けても、それが一貫していなければ、ブランドとして記憶には残りません。
お客様が触れるすべての接点で、「○○らしいな」と感じられること。
それを内側から支えるのが、“ブランド人格”という視点です。
■ブランドは、社内でふるまう“共通の人格”を持てているか?
これまでのコラムでは、外向きの発信や、体験の設計に注目してきました。
しかし今回は、「自分たちは、内側で何を拠りどころに行動しているのか?」という視点に立ち返ってみましょう。
私がかつて運営していたビジネスホテルでは、施設や料理は評価されていたにもかかわらず、口コミにはこうした声がありました。
・スタッフによってサービスの質にバラつきがある
・接客の印象が統一されていない
マニュアルを整備し、研修も重ねましたが、どれも表面的な対処にとどまりました。
根本には、「私たちはどんな存在か」という価値観が、社内で共有されていなかったことにありました。
■「ブランド人格」が、ばらつきを“価値あるふるまい”に変える
そこで改めて、「私たちは何者なのか」「お客様にとってどんな存在でありたいか」をチームで話し合い、言語化しました。
見えてきたのは、「宿泊は目的ではなく、手段」という視点です。お客様が本当に求めていたのは「部屋」ではなく、安心して明日を迎えるための拠点だったのです。
この洞察から、私たちの存在価値を「明日へのサポートベース」と定義し、ブランド人格を「明日を支えるコンシェルジュ」と表現しました。
そして、これを軸に、各部署ごとに役割を再定義しました。
・フロント → 不安を先回りする「安心の案内役」
・レストラン → 一日の始まりを整える「活力の提供者」
・清掃 → 空間全体に気を配る「快適空間の演出者」
こうした再定義は、単なる作業を「意味のあるふるまい」へと変え、スタッフ一人ひとりの意識も変わっていきました。
■ブランド人格は、文化を育て、行動に一貫性をもたらす
当初はサービスの質をそろえる目的で始めたブランド人格の設計でしたが、次第に企業全体が一つの人格のようにふるまえる組織へと変化していきました。
誰が対応しても、同じ価値観に基づいた行動ができる――
そんな一貫性が「誰に対応されても安心できる」という声につながり、ホテル全体の評価も向上しました。
この変化は、社外だけでなく社内にも波及しました。
お客様の声を通じて、「自分の仕事が誰かの明日につながっている」と実感したスタッフは、誇りを持って働くようになり、離職率も低下。
採用面でも、理念や価値観に共感する人材が自然と集まるようになりました。
つまり、ブランド人格の共有と実践がスタッフの行動を変えたことで、自発的な「インナーブランディング」の土台が築かれたのです。
■中小企業こそ、「強さ」ではなく「芯の通った在り方」で勝負する
ブランドというと、ロゴやパッケージなどの“見える要素”が注目されがちです。
しかし本質は、「どんな存在として記憶されたいか」を明確にし、それを日々のふるまいで体現し続けることにあります。
とくに中小企業にとっては、スペックや価格だけでは大手に勝つことは難しい。
だからこそ、自分たちらしい在り方=ブランド人格を軸に、ふるまいに一貫性をもたせ、顧客との信頼関係を築いていくことが、現実的かつ持続可能な戦略になるのです。
■ブランディングを育てる小さな問い
あなたの会社は、どんな人格として記憶されたいですか?
ブランド人格を考える際は、まず「顧客の本当の目的」に立ち返り、それに応える自社の存在意義を言葉にしてみてください。
・「挑戦をそっと支える“伴走者”」
・「毎日をちょっと豊かにする“暮らしのスパイス”」
・「自分らしさを引き出す“対話の名手”」
そんな人格が言語化されることで、日々の行動にも一貫性が生まれ、ブランドの“らしさ”が強く育っていくのです。
■次回予告
一貫した“らしさ”が整ったその先に、ブランドはどこへ向かうのか――
次回は、「共創」という視点から、ブランドが顧客と共に歩む未来を考えてみたいと思います。
第6回 ブランドは自走する~語られ、動き出すブランドへ~
「ブランディングって、結局なんだろう?」
そう思いながら、ここまで読み進めてくださった方もいらっしゃるかもしれません。
最終回では、企業の競争力の本質という視点から、「なぜ今、ブランディングが不可欠なのか」を掘り下げます。
その鍵となるのが、「ブランド資産(Brand Equity)」です。
■ブランド資産を築く「3 つの設計」
ブランド資産とは、顧客の認識、ロイヤルティ、信頼といった「目に見えない価値」の集まりです。
本連載では、その方法として「選ばれる価値」「記憶に残る体験」「信頼される人格」という3つの設計を紹介してきました。
この3つが連動することで、ブランド資産は戦略的に形成されていきます。
その結果、価格に依存しない競争優位性が生まれ、顧客は「少し高くても選びたい」と感じるようになるのです。
しかし、これらを築くだけでは、ブランディングは完結しません。
なぜなら、デジタル化によって、ブランドを取り巻く環境が大きく変化したからです。
■ブランドは“共創”の時代へ
かつてブランドは、企業が広告や宣伝を通じて一方向に発信することで、形成することができました。
しかし現在では、SNSやレビューといったユーザーによる発信(UGC:ユーザー生成コンテンツ)が広く浸透し、ブランドは企業だけで完結するものではなくなっています。
お客様がブランドを見つけ、共感し、体験し、それを誰かに伝える(共有)――そんな、「顧客の関与」が日常的に見られます。
この「発見から共有まで」の購買行動プロセスを整理したのが、電通が提唱する「DECAX」モデルです。
・Discover(発見):SNSや広告、投稿などを通じてブランドを知る
・Engage(共感):理念や世界観に共鳴し、関心を持つ
・Check(見極め):口コミや評価を調べ、納得感を得る
・Action(行動):実際に購入・体験してみる
・eXperience&Share(共有):体験を誰かに伝え、共有されていく
このプロセスを見てもわかるように、ブランドはもはや企業だけでつくるものではなく、顧客との共創によって育まれる時代になったのです。
だからこそ、企業は「単に商品を提供する」存在ではなく、顧客から「支持される」存在に変わる必要があるのです。
■ブランディングは「自走力」を育てる営み
では、「支持される」とは、どういうことでしょうか。
それは、顧客が単なる「買い手」から「担い手」や「発信者」へと変化し、自発的に企業の活動を支え、語り、広めるようになることです。
企業と顧客の間にそのような共創関係が築かれたとき、ブランドは企業の手を離れ、“自走”し始めます。
多くの人が「ブランディングがよくわからない」と感じるのは、“自走”の仕組みや成果が外からは見えにくく、あたかも「自然に起きている」ように映るからです。
実際、優れたブランドほど、なぜか人が集まり、語られ、選ばれていきます。
それどころか、「何もしていない」ように見えることさえあります。
「静かに」自走している状態――それこそが、ブランディングが“効いている”証です。
結局、ブランディングとは、「売るためのテクニック」ではなく、「自然に選ばれ続ける仕組み」をつくること。
単なる広報・販促の延長ではなく、企業の競争力を支える“中枢戦略”なのです。
だからこそ、ブランディングは一朝一夕にはできません。
まさに、“筋トレ”のような営みなのです。
そして、その成果は、集客や売上にとどまりません。
採用、人の定着、社内活性化、さらには社会からの信頼へと、着実に波及していきます。
■ブランディングは“儲け方の再設計”
声高に宣伝しなくても、人が集まってくる。
安売りしなくても、選ばれ続ける。
ブランディングとは、
5年後、10年後の選ばれ方を変えていく挑戦であり、
これからの企業経営における――“儲け方”そのものなのです。
■ブランディングを育てる小さな問い
――御社のブランドは、今、どこまで“自走”していますか?
本連載が、ブランドづくりの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
お問い合わせ
公益財団法人 千葉県産業振興センター総務企画部企画調整課 産業情報ヘッドライン
電話: 043-299-2901
ファックス: 043-299-3411
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
